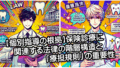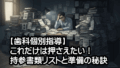歯科開業医の先生方へ
これまでの記事で、歯科個別指導は「罰」ではなく「業務点検」であること、そして指導には3つのタイプがあることを解説してきました。しかし、「なぜうちの医院が選ばれたのか?」という疑問は、常に先生方の不安の種になっているかと思います。
今回は、個別指導の対象となる医療機関が、誰によって、いつ、どのように選ばれているのか、その選定の裏側を明確に解説します。このプロセスを理解することは、自院のリスク管理と事前準備を行う上で非常に重要です。
🔎 誰が、いつ、どのように? 個別指導対象選定の仕組み
個別指導の対象となる医療機関は、決して**無作為(ランダム)に選ばれているわけではありません。そこには、公平性を担保するための明確な選定機関と、体系的なプロセス、そして根拠となる選定理由(端緒)**が存在します。
1. 誰が選ぶのか:地方厚生局の「選定委員会」による合議
指導対象の医療機関を選定するのは、各地方厚生局に設置されている**「選定委員会」**です。
- 構成員: 厚生局や都道府県の職員で構成されます。
- 決定プロセス: 様々な情報源から集められた情報を基に、公平な視点で審議し、指導対象となる医療機関を合議制で決定します。
- ポイント: 特定の担当官の独断で決まるものではありません。あくまで行政の公式かつ公平なプロセスによって、集団指導および個別指導の対象が決定されています。
2. いつ選定されるのか:前年度末に「年間指導計画」を策定
選定委員会は、主に前年度の2月から3月にかけて開催され、**次年度1年間の「年間指導計画」**を策定します。
- ポイント: 多くの個別指導は、突発的に行われるのではなく、行政の年間計画に基づいて計画的に実施されています。通知が届いてから慌てるのではなく、計画的な準備を行う猶予が与えられていると認識しましょう。
3. どのように選ばれるのか:必ず存在する「選定理由(端緒)」
指導の選定には、必ずそのきっかけとなる**「端緒(たんしょ)」、つまり根拠となる理由**が存在します。選定理由は、大きく以下の二つに大別されます。
A. 手続的・事務的な選定(不正の疑いとは限らない)
これらの選定は、行政の手続きや統計的な基準によって、事務的に行われるもので、不正請求を疑われているわけではありません。
- 新規個別指導:
- 新規開業から1年以内の医療機関が対象。これは制度上、全ての新規開業医に課せられる「通過儀礼」です。
- 再指導:
- 前回の個別指導の結果が**「再指導」となり、指摘事項に対する改善状況を確認**する必要がある場合。
- 集団的個別指導からの移行:
- 集団的個別指導を受けたにもかかわらず、**翌年度も引き続き「高点数」**の状態が続いている場合。
B. 情報提供に基づく選定(リスク管理の重要性が高い)
こちらは、外部または内部からの具体的な情報提供がきっかけとなるため、内容を伴った不適正な請求や診療体制の問題が疑われている可能性が高くなります。
- 患者からの情報提供:
- 「医療費通知の内容と窓口での支払額が違う」といった、レセプト内容や窓口会計の不審点に関する患者からの申し出。
- 保険者からの通報:
- 審査支払機関や保険者が、レセプトの内容に不審なパターンや、特定の歯科医院の請求傾向の異常を見つけた場合。
- 内部通報:
- 医療機関の現スタッフまたは元スタッフなど、内部事情に詳しい関係者からの情報提供。これは、労務管理やチーム内での情報共有体制の不備が、指導の端緒となり得ることを示しています。
⚠️ 自院のリスクを客観視する視点
このように、指導対象の選定は決してランダムではなく、明確な根拠に基づいて行われます。
「高点数だからいつか呼ばれる」と漠然と恐れるだけでなく、カルテ記載、請求事務、そして院内スタッフとの信頼関係において、これらの選定理由に該当するリスクがないか、日頃から客観的に見つめる視点を持つことが、個別指導を回避し、仮に通知が来た場合でも冷静に対応するための最良の防御策となります。
#歯科個別指導 #個別指導の選定理由 #選定委員会 #年間指導計画 #新規個別指導 #集団的個別指導からの移行 #情報提供に基づく選定 #内部通報 #リスク管理 #高点数
弊社のコンサルティング、サポート、研修会、
セミナー、サービス、商品に関する
質問・相談は下記フォームよりお寄せください。


会員規約 法人概要 プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく記載 免責事項
© 2024 一般社団法人 歯科歯科保険診療研修会